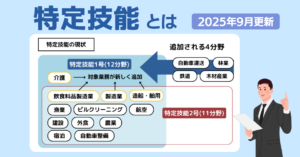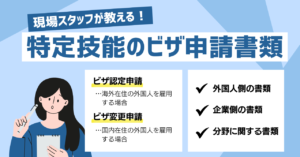【最新版】なぜ技能実習制度は廃止すべき?いつから、また新制度「育成就労」についても解説
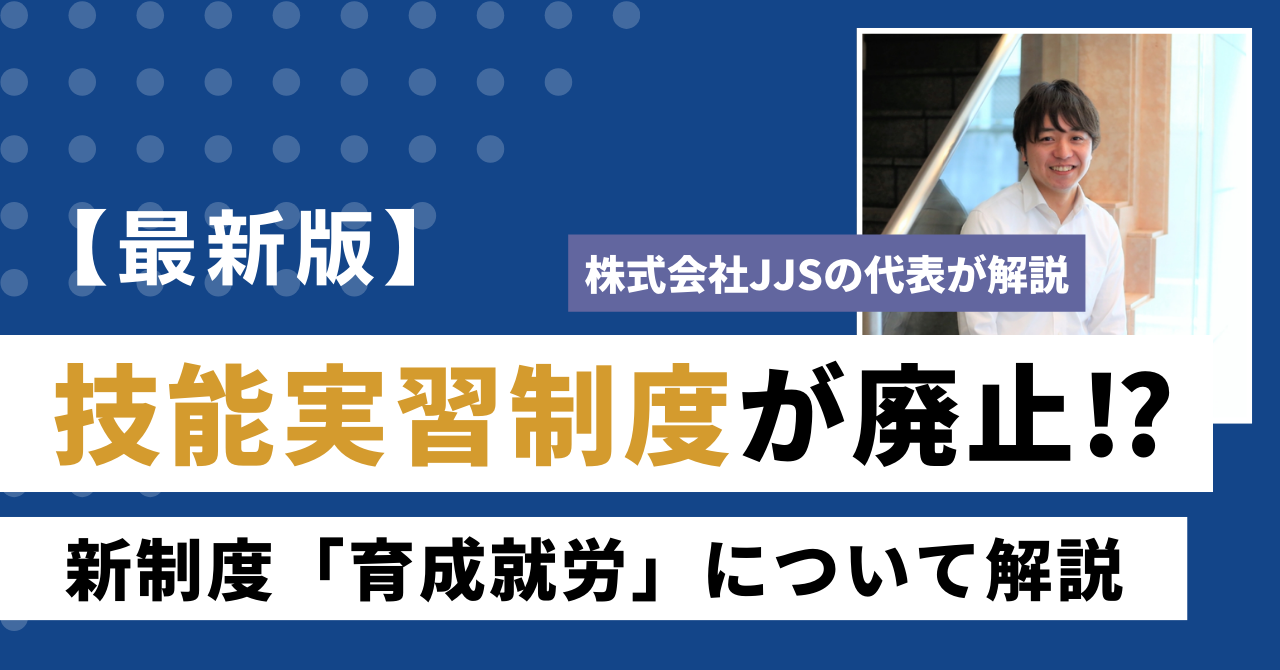
執筆者:松里優祐(株式会社JJS 代表取締役)
外国人技能実習制度を廃止し、人材の「育成と確保」を目的にした新制度創設を検討している政府の有識者会議が2023年10月27日に行われ、一定要件を満たせば、転職ができるなどの制限を緩和する最終報告書案を示しました。
技能実習から特定技能への移行をお考えの方
▶お気軽にお問い合わせください
1.そもそも技能実習制度とは
技能実習とは、1993年にスタートした国際貢献を目的とした制度であり、発展途上国人材に日本の先進技術を学び母国の発展に活かしてもらうための制度となります。
技能実習は母国への技能移転を目的としているため、3年もしくは5年たったら本国へ帰る必要があります。
特に人手不足と言われる建設業や製造業で多く受け入れられており、全国の技能実習生は2022年6月末時点で33万人もの数となります。
技能実習について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
2.技能実習制度はいつから廃止される?
2023年現在、技能実習生制度の廃止は確定のものではありませんが、有識者会議2023年秋に最終報告を政府に提出し、早ければ2024年の通常国会に関連法案が提出される可能性があります。そのため正式な変更は早くても2024年以降になります。
3.技能実習制度が廃止されるべきと言われる理由
技能実習制度は、本来、国際貢献を目的として作られた制度で、需給調整の手段として行われてはならないという基本理念を掲げていましたが、人手不足の業界を中心に労働力として受入をする企業が大半となり、制度の目的と実態の乖離が問題視されています。具体的にどのような点が問題視されているのでしょうか。
問題点①|転職ができない
技能実習生は「研修生」として来日し、労働者とは異なる扱いを受けるため、多くの制限があります。技能実習制度の下で、実習生は特定の雇用主に紐づいており、自由に転職することはできません。
これが原因で、実習生は適切な労働条件や賃金を保障されず、過酷な労働環境や人権侵害の状況に置かれることがあります。暴力やパワハラ、劣悪な労働条件は、技能実習制度が抱える深刻な問題とされています。
その場合、同じ実習先で実習期間が終了するまで我慢するか、職場から逃げ出すしかない状態となり、2022年に実習先の職場から逃げ出した技能実習生の数はおよそ9000人にのぼります。
参考:出入国在留管理庁「公表情報(監理団体一覧、行政処分等、失踪者数ほか)」
問題点②|多額の借金を抱えないと来日できない
実習生の5割以上が母国の送り出し機関や仲介者に手数料などを払うため、来日前に借金を背負っており、この点も問題視されています。
問題点③|国際的な批判
技能実習制度は、長年、国際的な批判にもさらされています。
米国務省の2023年次報告書でも、日本の技能実習制度が強制労働を含むと報告しており、「最低基準を完全に満たしていない」と評価しています。4段階評価のうち上から2番目の「対策不十分」に位置付けられました。
技能実習から特定技能への移行をお考えの方
▶お気軽にお問い合わせください
4.技能実習に代わる新制度「育成就労」の内容
以下の画像は、2022年12月から16回にわたり開催された有識者会議での議論を踏まえ、2023年11月30日に提出された最終報告書です。

引用:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議|出入国在留管理局
最終報告書等の内容を、以下、要約して解説していきます。
4-1.新制度の方向性
- 技能実習制度を人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
- 外国人材に我が国が選ばれるよう、技能・知識を段階的に向上させた上でその結果を客観的に確認できる仕組みを設けることによりキャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能制度へ円滑な移行を図ること
- 外国人の人権保護の観点から、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるとともに、監理団体・登録支援機関・受入れ機関の要件厳格化や関係機関の役割の明確化等の措置を講じること
- 外国人材の日本語能力が段階的に向上する仕組みを設けることなどにより、外国人材の受入れ環境を整備する取組とあいまって、外国人との共生社会の実現を目指すこと
参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議|出入国在留管理局
4-2.新制度と特定技能制度の関係性
新制度と特定技能制度の位置付けと関係性についても提言がありました。要約したものが下記になります。
- 技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、日本社会の人手不足分野における人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設する。人材確保に関しては、人権の保護を前提とした上で、地方における人材確保も図られるようにする。
- 新たな制度は、未熟練労働者として受け入れた外国人を、基本的に3年間の就労を通じた育成期間において計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指すものとする。
- 特定技能制度は、人手不足分野において即戦力となる外国人を受け入れるという現行制度の目的を維持しつつ、制度の適正化を図った上で引き続き存続させる。
- 家族帯同については、現行制度と同様、新たな制度及び特定技能制度(特定技能1号に限る。)においては認めないものとする。
- 現行の技能実習制度で行われている企業単独型の技能実習のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものについては、監理・支援手段等の適正化を図った上で新たな制度で引き続き実施することを可能とする。また、国際的に活動している企業における1年以内の育成のような、新たな制度とは趣旨・目的を異にするものであっても、引き続き実施する意義があるものについては、適正性を確保するための手段を講じつつ、既存の在留資格の対象拡大等により、新たな制度とは別の枠組みで受け入れることを検討する。
参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議|出入国在留管理局
5.受け入れ企業への影響
これまでの解説により、技能実習生や特定技能外国人労働者を既に雇用している企業には大きな影響があると考えられます。次に、これらの影響が日本の企業にどのようなものか、考えられる点を解説していきます。
一定の日本語能力を備えた人材を確保しやすくなる
2023年10月27日に行われた有識者会議では、日本語について次のように提言がありました。
- 就労開始前には、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)への合格又は入国直後の認定日本語教育機関等における相当の日本語講習の受講を要件とする。
- 特定技能1号移行時には、日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)への合格(ただし、当分の間は、当該試験合格に代えて、認定日本語教育機関等における相当な講習の受講をした場合も、その要件を満たすものとする。)を要件とする。
- 特定技能2号移行時には日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)への合格を要件とする。
- 受入れ機関による支援のインセンティブとなるよう、受け入れた外国人の日本語能力試験等の合格率など日本語教育支援に積極的に取り組んでいること等を確認するような要件を、優良な受入れ機関の認定要件とする。
以上のことから、外国人側には、特定技能への移行のための日本語学習の意欲の向上、企業、監理団体、支援機関側には優良受け入れ機関になるための日本語学習の提供意欲の向上が見込めるため、日本語レベルの高い外国人の雇用につながると考えられます。
受け入れに要したコストを回収しないまま外国人が転籍してしまう恐れがある
現行の技能実習制度では転職が原則不可であったため、一度受入れた技能実習生は3年間(技能実習2号)は雇用ができました。
新制度では一定要件あるものの、本人の意向による転職ができるため、「給料が安い」や「労働環境が悪い」と外国人が感じると転職される可能性があります。要件は以下のものが検討されています。
- 同一の受入れ機関において就労した期間が1年を超えていること
- 技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語 能力試験N5等)に合格していること
- 転籍先となる受入れ機関が、例えば受入れ中の外国人のうち転籍してきた者の占める割合が一定以下であることなど、一定の要件を満たす企業であること
転籍が緩和されたことにより外国人材が都市部に集中する可能性がある
日本での生活が慣れてきた外国人は、都市部へ転職をしたがる傾向にあります。そのため、地方の企業は、外国人が働きやすい労働環境への取り組みが求められるでしょう。
技能実習から特定技能への移行をお考えの方
▶お気軽にお問い合わせください
受入れ可能な人数・職種の範囲が狭まる
現行の技能実習制度においては、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと いう基本理念も踏まえ、受入れ見込数は設けられていません。
しかし、新たな制度は、特定技能制度と同様に人手不足分野における人材確保も目的の一つとするものであるため、日本人の雇用機会の喪失や処遇の低下等の防止、また外国人の安定的かつ円滑な在留活動を可能とするために現行の特定技能制度の考え方に則り、受入れ対象分野ごとに受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用します。
参考:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議|出入国在留管理局
6.まとめ
いかがでしたか。
今回解説した内容は、確定したものではなく、有識者会議にて検討されている事柄をまとめました。
しかし、今回解説した内容に変更される可能性はかなり高いため、今から準備を進めていくことをおすすめします。
弊社では、技能実習から特定技能への移行のご相談や、特定技能外国人の採用のご相談を承っております。
是非ともお気軽にお問合せください。




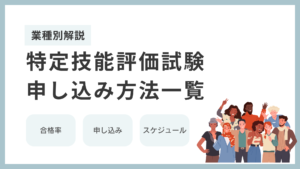

-4-300x169.jpg)